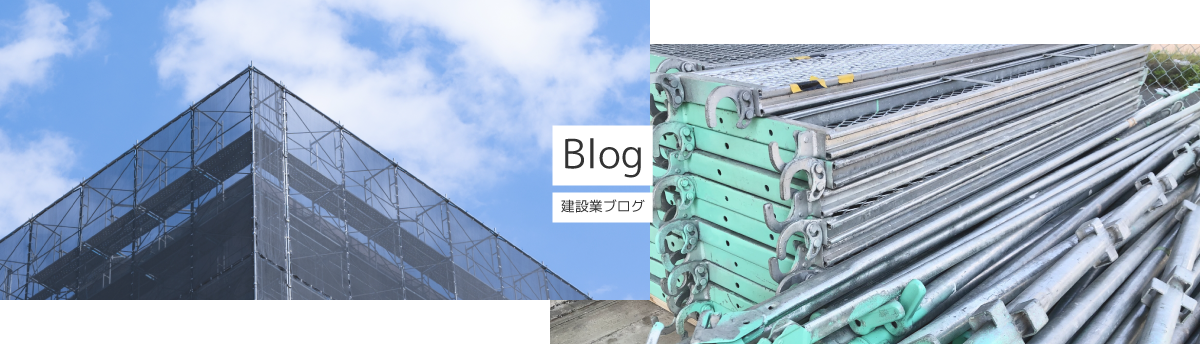老後に住宅のリフォームは必要? 4つのポイントと注意点を解説
老後に快適な暮らしを実現するには、自宅の補強やリフォームが必要になる場合も少なくありません。老後に備えて住宅を整備するうえでは、さまざまなポイントを押さえておく必要があります。この記事では、老後のためのリフォームについて検討している人に向けて、リフォームのポイントや注意点などを解説します
ぜ老後のためのリフォームが必要なのか?
ここでは、老後のためにリフォームを検討する理由について解説します。
家庭内事故を防止するため
高齢になると体力や体の機能が低下するため、自宅で転倒したりヒートショックを起こしたりする可能性が高くなります。高齢者の家庭内での事故はとても多いです。
自宅にわずかな段差があっても、若いうちはあまり気になりません。しかし、年を重ねてくると、わずかな段差でもつまずきやすくなります。また、住宅に長く住み続けていれば、建物や設備が劣化して事故の原因になる場合もあります。家庭内で発生する事故を防ぐには、リフォームにより自宅の安全性を高めることが重要です。
自宅の老朽化や災害時の対策を行うため
若いときから同じ住宅に住んでいれば、自分が歳を重ねるほど住宅も古くなります。建物や設備が劣化すると事故の原因になるだけでなく、日常生活にも支障をきたす恐れがあります。老後も快適な生活を維持するには、リフォームによる改修が必要です。
また、住宅が老朽化していると、地震や台風などの災害発生時に被害を受けやすくなります。住宅の安全性を高めたり、停電時に蓄電池を使えるようにしたりするためのリフォームするケースも多くなっています。
老後のためのリフォームで意識したい4つのポイント
老後を見据えたリフォームでは、特に意識したいことがあります。具体的な4つのポイントを解説します。
断熱リフォーム
断熱リフォームは、住宅の断熱性を高めるための施工方法です。冬場は暖かい部屋と寒い部屋の温度差が大きくなりやすく、ヒートショックを起こす原因になります。ヒートショックとは、激しい温度変化により、脈拍が急激に速くなったり血圧が急上昇または急降下したりする現象です。ヒートショックを起こすとめまいや心筋梗塞などを引き起こすリスクがあります。
断熱リフォームで住宅の断熱性を高めて部屋と部屋の間で激しい温度差が生じないようにすると、ヒートショックの予防に効果的です。
バリアフリー化
若い頃は危険を感じなかった場所も、年齢を重ねると思わぬ事故につながるリスクが出てくる場合もあります。高齢になっても安全に生活できるようにするには、住宅のバリアフリー化が必要です。たとえば、なるべく段差をなくしたり、手すりをつけて安全に移動できるようにしたりする家庭が多いです。
また、車椅子での生活を想定し、スペースに余裕をもたせる場合もあります。開き戸を引き戸に替えて出入りしやすくするのもおすすめです。
間取りの変更
年を重ねてライフスタイルが変化し、現在の生活にあわせて間取りを変更するケースもあります。たとえば、子どもが独立して個室が余っている場合は、部屋の仕切りをなくすと広々とした空間として活用できます。
また、夫婦が適度な距離感で暮らすため、自分たちの生活にあわせて間取りを変更するのもひとつの方法です。たとえば、キッチンや書斎などのスペースを広げ、夫婦それぞれが趣味を楽しめるようにしている家庭もあります。
耐震性の強化
住宅の築年数によっては、現行の耐震基準を満たしていない場合もあります。1981年以前に建てられた住宅は旧耐震基準をもとにしており、十分な耐震性を備えていない可能性が高いです。大きな地震に耐えらず倒壊する恐れがあるため、リフォームによる耐震補強をしたほうが安心です。たとえば、リフォームで既存の壁の強度を高めたり屋根を軽くしたりすると、耐震性を強化できます。
老後のためのリフォームで活用できる補助金制度・減税制度
老後のためにリフォームする場合は、補助金制度や減税制度などを利用できる可能性があります。具体的に解説します。
長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金
住宅の性能を高める目的でリフォームする場合は、長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金を活用できます。リフォームにかかる費用の一部を国に負担してもらえる制度です。たとえば、住宅の省エネルギー化や耐震補強なども対象になります。
補助を受けるには、インスペクションの実施や、リフォーム履歴と維持補元計画書の作成などが必要です。また、リフォーム後の住宅が一定の基準を満たしている必要があります。
介護保険制度
バリアフリー化のためにリフォームするなら、介護保険から助成を受けられる可能性もあります。対象となるのは、介護保険制度で要介護または要支援に認定されている場合です。住宅のバリアフリー化のための改修が必要だと判断されると、助成を受けられます。
対象となるリフォーム費用の上限は最大20万円です。20万円の工事費のうち、9割にあたる18万円が助成されます。担当のケアマネージャーや地域包括支援センターに相談すると、スムーズな申請が可能です。
各自治体の補助金制度
自治体のなかには、リフォームに対する補助金制度を独自に設けているところもあります。国が住宅の改善に力を入れているため、それにならってリフォームを推進している自治体が増えています。ほかの補助金を受けられない場合でも自治体の補助金制度なら活用できる可能性があるため、リフォームを検討する際は確認してみましょう。
「一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会」の公式サイトでは、自分たちが住んでいる地域で活用できる補助金制度を検索できます。
※参考:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会
リフォーム減税
条件を満たしてリフォームを実施すれば、減税になる場合があります。対象となる税の種類は、所得税、固定資産税、贈与税、登録免許税、不動産取得税です。
所得税の控除は3つにわかれており、投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税があります。投資型減税はローンの利用の有無にかかわらず選択できます。ローン型減税は償却期間5年以上、住宅ローン減税は償却期間10年以上のローンが対象です。
老後のためのリフォームを行う際の注意点
老後のためのリフォームは、工事の内容によって工期が変化します。大掛かりなフルリフォームをするには、着工から完成まで長い期間が必要です。老後を見据えてリフォームする場合は工事の流れを理解し、余裕をもって早めに計画を立てましょう。
住宅の劣化の状況によっては、追加工事が必要になるケースもあります。万が一の場合に備え、予算には余裕をもたせておくと安心です。
老後のためのリフォームにおける業者の選び方
老後を見越してリフォームするときは、業者選びにもこだわりましょう。ここでは、業者の選び方について解説します。
実績が豊富か
住宅のリフォームを失敗しないためには、信頼できる業者を選ぶことが大切です。実績が豊富であり、さまざまなニーズに対応してきた業者を選びましょう。業者のホームページをチェックすると、具体的な実績を確認できます。業者の得意分野についても把握し、自分たちが希望するリフォームに対応できるか見極める必要があります。
口コミも見ておくと、過去にその業者へ依頼した人の率直な意見も確認できます。
サポートは充実しているか
リフォームを依頼する業者を選ぶときは、サポート体制も確認しましょう。なかには、リフォームが完了して実際に住み始めた後に不具合や欠陥がみつかるケースもあります。サポート体制が充実していないと修理に対応してもらえない恐れもあるため、注意が必要です。
アフターサービスがついている業者を選べば、たとえ後から問題がみつかってもきちんと対応してもらえます。責任をもってリフォームの工事をしてもらえるため、安心です。
まとめ
体力やライフスタイルの変化を見据え、老後に向けたリフォームをする家庭は多いです。バリアフリー化や耐震補強などを実施すると、長く安心して暮らせます。補助金や減税制度も活用すれば、少ない負担で住環境を整えられます。信頼できる業者を選び、理想的なリフォームを実施しましょう。